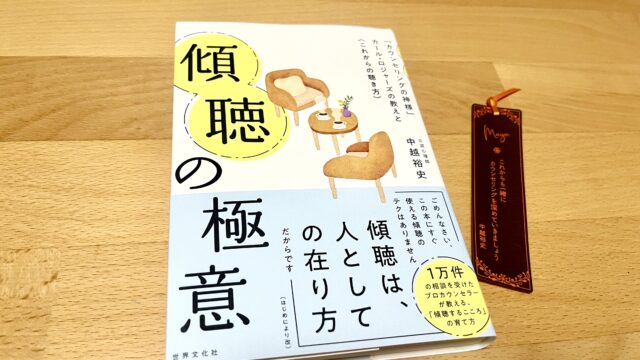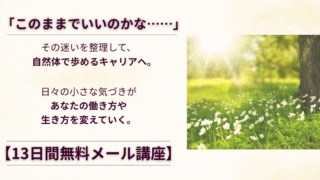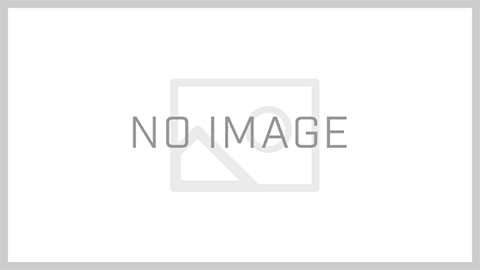身近な人の死をどう乗り越えるか──祖母との別れで感じた悲嘆のプロセス
こんにちは。
心理カウンセラーの矢菅まゆです。
少し久しぶりの更新になります。
今日は
これまでとは異なるテーマで、
「身近な人を失う悲しみ」について
書いてみたいと思います。
家族や友人、恋人──
大切な誰かを失う経験は、
誰にとっても深い悲しみを伴います。
そんなとき、
どう心を保てばいいのか。
私自身の体験が少しでもヒントになればと思い、
お伝えしていきます。

祖母の死をきっかけに思い出した「悲嘆のプロセス」
先日、
8月11日の夜に、
遠方に住む父方の祖母(98歳)が亡くなりました。
本来であれば、
その5日後に祖母の家へ泊まる予定でした。
けれども、
そのまま葬儀へと変わってしまいました。
葬儀などを終えて関東へ戻ってきたとき、
ふと思い出したのです。
「そういえば、
身近な人の死を乗り越えるプロセスについて、
どこかで読んだことがあったな。
あのプロセスの名前は何だっただろう。
もう一度確認して、
祖母の死を受け入れる手がかりにしたい。」
そう思い立ち、
「身近な人の死を乗り越えるプロセス」
と検索しました。
このブログでは、
私自身の経験を交えながら、
そのプロセスについて紹介していきます。
これまで私は心理カウンセラーとして、
キャリアのことや働くことにまつわる
悩みを中心に発信してきました。
そのため今回のことをここに書くかどうか、
正直迷いました。
けれど、
文字に起こすことが、
私自身が祖母の死を受け入れていくことに
つながると思いました。
また、同じように
身近人なとの別れに向き合っているかたにとって、
その悲しみに少しずつ折り合いをつけていく
ヒントになればと思い、
発信させていただきます。
グリーフ(悲嘆)とそのプロセス
皆さんは「グリーフ」という言葉を
耳にしたことはあるでしょうか。
日本語では「悲嘆」と訳され、
大切な人を失ったときに感じる深い悲しみや、
それに伴うさまざまな心の反応を指します。
身近な人との別れを経験すると、
・ショックで頭が真っ白になったり
・現実を受け入れられなかったり
・怒りや後悔、孤独感でいっぱいになったり
することがあります。
こうした反応は異常ではなく、
むしろ自然な心の働きだと言われています。
※詳しい解説はこちら
https://www.grief-care.org/about.html
悲嘆の中で起きる心の動きは
人それぞれですが、
これまで「悲嘆のプロセス」
として整理されてきました。
そのひとつが、
アルフォンス・デーケン氏による
「悲嘆の12段階」です。
※すべての人が必ずこの順序をたどるわけではなく、
行ったり来たりすることもあります。
悲嘆の12段階(アルフォンス・デーケン)
1.精神的打撃と麻痺状態
大切な人の死に直面し、頭が真っ白になったような衝撃を受ける段階。2.否認
死を認められず、否定してしまう段階。
突然死の場合は、否認が顕著に表れる。3.パニック
死を確信するが、否定したい感情が合わさり、パニックとなる段階。4.怒りと不当感
「なぜ自分がこんな目に」と理不尽さを感じ、怒りが湧き上がる段階。5.敵意とうらみ
周囲の人や故人に対して、やり場のない感情を敵意という形でぶつける段階。6.罪意識
「もっとこうしてあげればよかった」と自分を責める段階。7.空想形成・幻想
故人がまだ生きているかのように思いこみ、実生活でもそのようにふるまう段階。8.孤独感と抑うつ
葬儀などが一段落し、途端に寂しさが募る段階。9.精神的混乱とアパシー(無気力)
生活目標を見失い、どうしていいか分からず、関心を失う段階。10.あきらめ‐受容
自分の置かれた状況を受け入れ、つらい現実に向き合おうと努力が始まる段階。11.新しい希望‐ユーモアと笑いの再発見
こわばっていた顔に、微笑みが戻り始める段階。12.立ち直り‐新しいアイデンティティの誕生
立ち直りの段階。
悲嘆のプロセスを経て、新たなアイデンティティを獲得する。
このように整理されることで、
「自分はいまどの段階にいるのか」
を理解したり、
「これは自然な流れなんだ」
と安心することができます。
私が経験したプロセス
悲嘆のプロセスは、
人によって歩み方も順序も異なります。
私の場合はざっくりいうと、
1・2・6・8の段階を経験し、
今は10の段階の過程にいると感じています。
ここでは特に印象的だった2の段階と
10の段階の体験について、
少し書いてみたいと思います。
第2段階:否認
祖母が安置されている葬儀場へ行きました。
棺のそばには、
見覚えのある祖母の遺影が飾られていました。
けれども、
棺の中にいた祖母は厚化粧をされていて、
まるで蝋人形のよう。
遺影の中の祖母と、
目の前の祖母との差が大きく、
棺の中にいるのが本当に祖母なのかどうか、
頭が混乱していました。
棺の中の祖母は、
見覚えのある服を着ていました。
「ああ、やっぱり祖母なのだ」
と思う一方で、
厚化粧をされた顔は蝋人形のようでリアリティがなく、
受け止めきれない気持ちが続いていました。
棺や葬儀場の装飾は
「これは現実なのだ」
と突きつけてきます。
それでも、
私はますます現実を
信じられなくなりました。
そのときの私は、
まさに「否認」という段階の
ただ中にいたのだと思います。
第10段階:受容
今こうして、
自分の思いや体験を書いていることそのものが、
祖母の死を少しずつ受け入れていくことに
つながっていると感じます。
受容とは、
突然「納得する」ものではなく、
こうして一つひとつ言葉にしながら、
少しずつ心に落とし込んでいく
プロセスなのだと感じています。
家族の姿を見て思ったこと
祖母の葬儀などで祖母宅にいた間、
私は孫という立場で過ごしていました。
その一方で、
祖母の子どもである父や叔母は、
大人として現実的な対応に追われていました。
葬儀の手配やお金のこと、
家の中の書類整理、
祖母が契約していた各種サービスの解約──。
次から次へとやらなければならないことが押し寄せ、
悲しみに浸る時間は
あまりなかったのではないかと感じています。
私自身も祖母を亡くした悲しみはありますが、
父や叔母と比べると
「喪主側の責任」は背負っておらず、
思い出の総量も異なるでしょう。
だからこそ、
彼らが本当に自分の気持ちを
吐き出すことができているか、
あとからふとした瞬間に
寂しさが押し寄せるのではないか──
そんなふうに、
少し心配になりました。
あとから寂しさや悲嘆が
押し寄せたときに必要になってくるのが、
「グリーフケア」という援助です。
グリーフケアとは、
グリーフ(悲嘆)反応が起こっている人の
気持ちに寄り添い、
悲しみを癒すサポートをすることです。
「誰かに話す」
「涙を流す」
「思い出を語る」
「お別れの儀式を用意する」
──どれも立派なケアになります。
湧き上がる感情を否定せず、
安心して思いを吐き出せることが、
また顔を上げて生きていく力につながります。
さいごに──あなたへ
今こうして、
自分の思いや体験を書くということそのものが、
私にとって受容のプロセスに
なっていると感じています。
もし今、
大切な人を失った
悲しみの中にいる方がいたら──。
「今私は、
こういうステップのさなかにいるのか」
と知ることで、
ほんの少しだけでも安心して、
悲しみに向き合うことができるかもしれません。
そして、
これからその局面を迎える方にとっても、
「悲嘆にはプロセスがある」
と知っているだけで、
心の準備が少し違ってくると思います。
この記事が、
あなたの心のどこかに残って、
いつか支えになる瞬間があれば、
これほど嬉しいことはありません。
※今回の出来事について、
noteでも記載しています。
このnoteでは
「祖母との出来事と私の感情」
に主軸をおいています。
良かったらこちらも併せて読んでみてください。
心理カウンセラー
矢菅まゆ