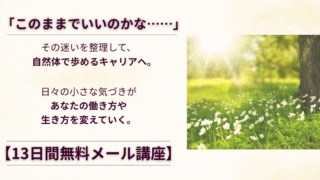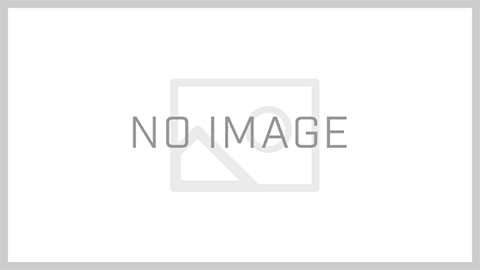真面目な人ほど危ない?“社風”に染まりすぎて苦しくなる理由
こんにちは!
心理カウンセラーの矢菅まゆです。
周りの期待に応えたいと、
一生懸命働いてきたあなたへ。
「会社の考え方にどこかモヤモヤする…」
と思いつつも、
「自分がズレてるのかな」
と思ってしまう。
そんな方はいませんか?
今日はそんなあなたにこそ伝えたい、
「文化中毒」という考え方についてお話しします。

文化中毒ってなに?
職場には、
それぞれに独特の「社風」や「雰囲気」があります。
たとえば
「上下関係がはっきりしている」
「フラットで自由な空気」
「体育会系で活気がある」
など。
就職活動のときに聞く
“社風”という言葉で表されるような、
実際に働いてみないと分からない感覚のこと。
人によって感じ方もさまざまですが、
なんとなく職場に流れている
“空気感”のようなものかもしれません。
この「社風」とよく似た言葉として
「組織文化」という言葉があります。
社風が“肌で感じる空気感”だとすれば、
組織文化はその空気を生み出している“土台”のようなもの。
たとえば、
会社の理念や行動指針など、
明文化されたルールや価値観。
それに加えて、
「朝は始業30分前に出社するのが当然」
「昼休みは新人が一番最後にとる」
といった、
“暗黙の了解”のようなルールも含まれます。
こうした文化のなかで働いていると、
いつのまにかそれが「当たり前」になっていきます。
もちろん、
それが悪いわけではありません。
むしろ、
自分の価値観と合っているかどうかは、
転職などでも大事な判断軸になりますよね。
ただ、
もし違和感を抱いたとしても、
「きっと自分がズレてるんだ」
と打ち消してしまうことがある。
そうやって疑問すら持てなくなり、
会社の価値観をそのまま自分に取り込んでしまう。
このように、
組織文化に強く影響されすぎて、
自分の本音や感覚を見失ってしまう状態のことを、
批判的経営研究(CMS)では
「文化中毒(cultural dopes)」と呼びます。
※「組織文化研究における批判的経営研究(CMS)の可能性」
(竹中克久,2017年)より引用
一見優秀で、
“会社になじんでいる人”に見える文化中毒。
でもその内側では、
視野がどんどん狭まり、
違和感にフタをし続けた結果、
心の中に無理や我慢が積み重なっていく。
そして、
知らず知らずのうちに心がすり減ってしまうのです。
なぜ“真面目な人”がハマりやすいのか
文化中毒という言葉だけを聞くと、
「そんなの自分とは無関係」
と感じる人もいるかもしれません。
でも実はこの状態、
とても真面目な人ほど
ハマりやすいという側面があります。
たとえば、
人の言葉を素直に受け止める。
期待に応えようとする。
自分の中に芽生えた違和感よりも、
「私の方が未熟なのかも」と考えてしまう。
——そんな方ほど、
知らないうちに
組織文化を深く吸収していきやすいんです。
私自身も以前、
気づかないうちにその状態に近づいていたと思います。
前職では、
企業の差別化のポイントは「文化」である、
という考え方がありました。
そのため企業理念や行動指針、
価値観などを理解し、
体現することが大切にされていました。
ありがたいことに私は、
「当社の文化をよく理解し、
体現してくれている」と、
マネージャーからほめていただいたこともあります。
ですが今振り返ると、
それは素直に染まりすぎていた側面がありました。
当時の私はスポンジのように、
会社の文化を吸収していたのです。
でも、
少しずつ自分の中で、
うまく言葉にならない違和感が生まれていきました。
「本当はそんなに割り切れない」
「でもそれを言ったら“甘え”だ」
「だったら、黙って従った方がいいよね」
そんなふうに、
自分の感覚を抑えこむようになっていったのです。
ただ当時は、
抑え込んでいる、
とういう自覚もありませんでした。
もちろん、
会社や組織にある程度なじむことは、
社会人として必要な面もあります。
でもそれが、
自分の気持ちや価値観を押し殺してまでの
「適応」になると、
それはもう、
自分自身をすり減らしてしまう働き方になってしまいます。
文化中毒が引き起こすもの
文化中毒の厄介なところは、
その状態にあることに、
なかなか自分では気づけないという点です。
組織の価値観に従って動いているうちに、
それが「当たり前」になっていく。
自分の中にふと湧いた疑問や違和感も、
「ここではそういうものだよね」
と飲み込んでしまう。
気づけば判断軸が、
「会社の基準」になっていくんです。
何かに悩んだときも、
「私はどう感じているか?」ではなく、
「会社的にはどうあるべきか?」
で考えてしまう。
もちろん、
そう考えることが必要な場面もあるでしょう。
けれど、
ずっとそのモードで働き続けると、
だんだんと自分の輪郭が
ぼやけてくるような感覚に陥っていきます。
私も当時、
まさにそうでした。
会社の価値観を自分の中に取り込みすぎて、
「ちゃんと体現できる人でいたい」
と思うようになっていました。
でも実際には、
思うように振る舞えなかったり、
言葉と行動の間にズレがあったりして、
どこかで理想の社員像に届かない自分を、
つい責めてしまっていた。
誰かに何か言われたわけでもないのに、
「もっとできるはずなのに」
「こんな自分じゃダメだ」と、
その矛先が自分に向いてしまっていたんです。
そして、
心と体のバランスが崩れはじめた頃には、
「周りの人と同じようには、
もう頑張れない……」
という状態になっていました。
今思えば、
“組織に適応しようとするあまり、
自分の声を置き去りにしていた”
——それが、
当時の私を苦しめていた根っこだったのだと思います。
文化中毒から抜け出すヒント
文化中毒は、
自分でも気づかないうちに
少しずつ進行していくものです。
だからこそ、
大きく変わろうとしなくて大丈夫。
まずは
「小さな違和感」に気づくことが、
第一歩になります。
「この会社が合っていると思って入ったのに、
合わないと感じるのは自分が未熟だから」
というわけではありません。
その違和感は、
あなたの感性が発している大切なサインです。
たとえば、
「なんかしんどいな」
「これは本当に自分が望んでること?」
そんなふとした“引っかかり”を、
そのままにせず言葉にしてみること。
書き出してみるのもいいですし、
誰か信頼できる人に話してみるのもおすすめです。
このとき、
できれば会社の人以外に話すのが理想です。
というのも、
同じ文化の中にいる人と話すと、
その文化の正しさが前提になりやすく、
かえって文化中毒を強めてしまうリスクがあるからです。
たとえばカウンセリングなど、
組織の外の中立的な人に話すことで、
あなた自身の「本来の価値観」
に立ち返るヒントが得られるかもしれません。
大切なのは、
「うちの会社ではこう考える」ではなく、
「私はどう感じているんだろう?」
という視点に立ち戻ることです。
私自身、
文化中毒に近い状態に陥っていたときは、
頭では「こうあるべき」ばかりで、
自分の気持ちや感覚を完全に置いてけぼりにしていました。
でも、
「自分の本音」に耳を傾けるようになってから、
少しずつ、
心に余白が生まれていった気がします。
真面目さは、
あなたの強みです。
でもそれは
「自分をすり減らすための強さ」ではなく、
「自分を大切にする力」
として使ってほしいと願っています。
あなたがあなたらしく働ける場所は、
きっとあります。
まずは、
今感じているその違和感に、
そっと耳を傾けてあげてくださいね。
あなたのこれからのキャリアを、
人生を、
心から応援しています。
心理カウンセラー
矢菅まゆ